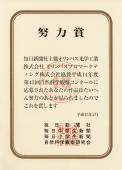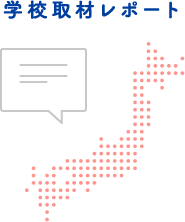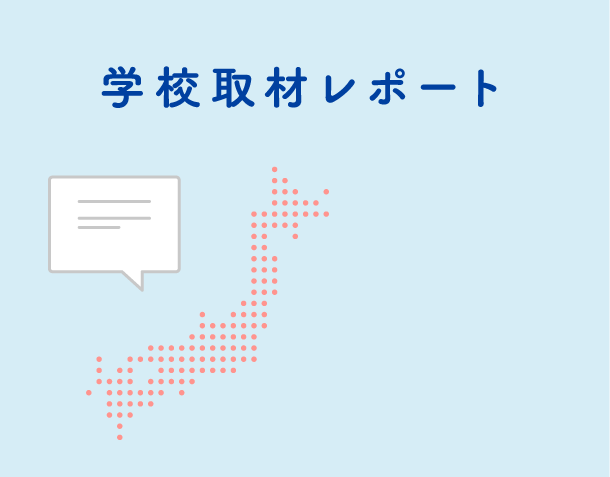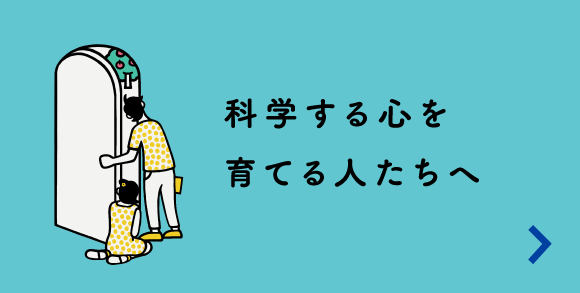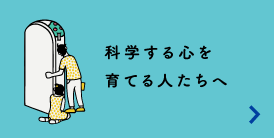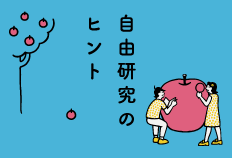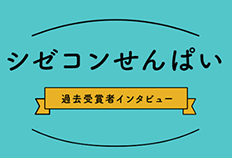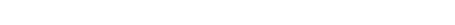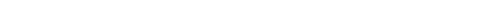大田区立南六郷中学校
取材
オリジナリティーあふれる研究をコツコツと
第50回自然科学観察コンクールで佳作(中学校の部)に輝いた力作が宇宙科学部の作品だ。顧問の小森信男先生は指導奨励賞を受賞、小森先生はこれがシゼコンへの初めての応募である。「岩石の風化変質実験」の継続研究にかける熱い思い、授業でのさまざまな工夫などについて語っていただいた。
宇宙科学部のホームグラウンドは理科室
夜空に輝く赤い星、火星。私たちは「火星はなぜ赤いのか?」と考えてみたことがあるだろうか。このテーマに毎日コツコツと取り組んでいる中学生たちが東京・大田区にいる。運動部の歓声がグラウンドに響き渡る放課後、南六郷中学校の第二理科室では宇宙科学部のメンバーが真剣な面持ちで研究の真っ最中。佳作を受賞した『紫外線と水によるカンラン石・炭素・金属の変化』はこの部屋から誕生した。
少数精鋭でレベルの高い研究を
宇宙科学部の部活は月曜から金曜までの毎日。夏休みもほぼ休みなく理科室に通うという。 |
理科準備室には部員が手作りした |
実験装置も工夫して手作り
実験に必要な装置は自分たちの手でゼロから作り上げる。薄手のアルミニウム板、ガムテープ、粘土など身のまわりにある素材を駆使して装置を組み立てているのは、部長でもある髙橋尚人君(3年生) だ。「大人は複雑に考えがちですが、彼はいとも簡単に必要な装置を作ってくれます。まさにスペシャリストです。興味あることを継続してデータを積み重ねていけば中学生でも科学者と同等の研究ができるよ、と部員にはいつも話しているんです」
コンクールへの応募を励みに
小森先生は自由研究の大切さについても熱く語る。 「自由研究は理科そのものです。自然を調べて法則性を発見し、それを人間生活に役立てることが理科の役割だよ、と授業でも常に言っております。自分の興味があることを楽しみながら調べてもらいたいですね」4月の最初の理科の授業で、夏休みには宿題として自由研究があること、優れた作品はコンクールに応募することを伝える。昨年度は学年全体の8割ほどが提出、その中から約3分の1にあたる57作品を選んでシゼコンに応募した。
「理科コンクールへの応募はとても重要だと考えています。発表の場があることで生徒に自信がつくし、またモチベーションにもなるからです。宇宙科学部が佳作をいただき、全校朝礼で表彰されたことで頑張りがわかってもらえたし、立派な副賞も励みになりました」
ノートに励ましのコメントを
|
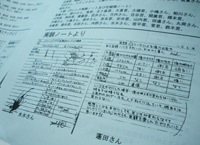 週に一度、発行している「理科通信」。 |
「自主学習ノート」と「理科通信」
授業ノート以外にも「自主学習ノート」を併用、1~2年生には教科書の要点を自分なりにまとめること、3年生には問題集を自分のペースで解いてポイントをまとめるように指導する。この自主学習ノートも定期的に提出させ、励ましのコメントを記入している。
授業ノート、自主学習ノートとも、上手にまとめてあるものはスキャンして、週に一度発行する「理科通信」( A4、4ページ) に掲載する。このように理科通信には、生徒の活躍や努力した点をできるだけ載せている。また勉強法のアドバイスや最新の科学ニュース、科学者の伝記等を、学習状況に応じて掲載している。これらは長年の経験から編み出された「やる気と学力を高める工夫」なのだ。
教師も自分の研究テーマを持とう
宇宙科学部の「岩石の風化」というテーマは小森先生自身のライフワークでもある。硬い岩石も刺激を与えられることでバラバラになる……。大学院のころ、岩石の風化変質実験を目の当たりにした時の感動が今もずっと続いている。
「前任の品川区立八潮中学校では、天文地学部で酸性雨が岩石に与える影響を調べていました。ある時、塩酸を石にかけたら鮮やかな褐色に変わった。これは火星の岩石にそっくりだと思ったことが、岩石と天体を結び付けるきっかけになり、今の研究に至っています」
理科教師も自分が好きなこと、興味あることをもっと研究するべきだ、と小森先生は考える。
「授業を工夫することはもちろんですが、自分なりの研究テーマを深めていくことによって自然科学の本質を生徒に力強く伝えられると思うからです」
世界に誇る「ものづくりの街」で
ここ六郷地区は伝統的に「ものづくり」の気質がある、と小森先生。「このエリアには世界的に注目される、独自の技術を持った工場が数多くあります。宇宙科学部もわずか5人の小さな部ですが、他にはないオリジナリティーあふれる研究を行っています。そこに共通性を感じています」
天空の彼方、火星の謎を解き明かす仮説がこの第二理科室から生まれるかもしれない。今日も小さなスペシャリストたちと一緒に小森先生は研究を続けている。毎日コツコツと継続することがやがて大きな力になることを信じて。

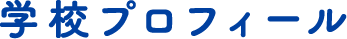
電話 03-3732-9351

小森信男先生(53 歳)
進路指導主幹
理科担当(1年生)
宇宙科学部顧問
中野区立桃花小学校
取材
地域に開かれた理科教育を目指して
「桃花自然応援隊」
|
2年間かけて「変形菌」を研究
昨年度、寺田先生は桃園第三小で6年生のクラスを受け持っていた。そのクラスの中に、第48回自然科学観察コンクール( 平成19 年度) で佳作を射止めた伊知地直樹君がいる。『変形菌はどのように餌を見つけるのか?』という作品だ。
「伊知地君は5年生の時から変形菌に興味を持って、土日ごとに博物館へ通っては学芸員の方に教えを請うたり、自分でも変形菌( モジホコリ) を飼って観察しながら、ずっとこのテーマを追いかけていました。彼はほかの子供たちからも尊敬される存在だったので、入賞して校長先生から朝礼で表彰された時には『やっぱりすごいなぁ』という反応でした」
伊知地君は5年生の時にも『ふしぎな生き物 変形菌』という作品を応募している。継続することで研究の深さを増していった。
「コンクールに応募するかどうかは、子供たちにまかせています。特に何も言わなくても、みんな自然科学観察コンクールのことを知っていて、早くから応募を目標にがんばる子もいます」
昨年度は計46人が夏休みの自由研究を応募した。自由研究は全員必須で、9月に提出された作品は、クラスごとに教室内に展示する。
「発見ノート」で発見や感動を共有
| 昨年度は指導奨励賞、第45回( 平成16年度) には指導特別賞を受賞している寺田先生だが、「私は本当に特別なことは何もしていないんですよ」とあくまで控えめ。 「でも、自由研究をまとめるための文章力や構成力は、毎日の『発見ノート』が役に立ったかもしれません」 「発見ノート」とは、学習帳に自分なりの日々の発見を綴って提出するもの。長さやテーマは自由。これを毎日読んでは朱入れしてコメントをつけて返却する。面白いトピックスは皆の前で読み上げたり、「これは」という文章は増し刷りして全員に配るなど、一人の発見や感動をクラスで共有できるように心がけた。「夏休みには何を研究するか考え中です」と早い時期に書いてくる子供がいれば、それを皆に紹介することで、「自分もそろそろ考えなくちゃ」という種をまく。 「即、効果は出ないかもしれないけれど、10人中1人にはヒットするかもしれない。伊知地君は休日に訪ねた研究所のことなどをよく書いていました」 |
 樹木には名前のプレートが付いている |
「プロジェクト学習」でまとめる力を
| 「総合の時間」には、2 ~ 3 カ月のスパンでひとつのテーマに取り組む「プロジェクト学習」を行った。「技あり、にっぽん」というテーマで日本の工業をとりあげた時は、まず、曲がるストローを開発した地元のアイデア社長をゲストティーチャーとして招いた。さらに日本にはどんな技術があるか、江戸切子などの伝統産業から最先端のロボット「アシモ」までを調べ、最終的には劇にまとめて学習発表会を行った。 「プロジェクト学習では問題解決能力や自分で調べたこと、わかったことをどう表現するかという力をつけました。それが夏休みの自由研究にも発揮されるといい作品になります」 6月下旬の移動教室( 隔年で軽井沢と福島) も格好の素材。例えば「まるごと軽井沢」というテーマのもと、自然・産業・歴史などに分かれてグループで調べ学習を行った。 「自分の興味をポイントをしぼって事前に調べ、現地でそれを修正したり、付け加えたり、新しく発見したりという体験は、子供たちにとっても『やった!』という充実感が得られますね」 |
 親子2代で通うケースも少なくない |
自由研究は集大成
| 「どんな科目にも共通しているのは、最初が肝心ということ。“ やりたい” という気持ちが学力の始まりだと思うので、意欲を高めるためにはどうしたらいいかを考えます。いかに子供が飛びつくような授業を最初に提供できるかですよね」 理科の授業でも、「てこの原理」の項目では、実際に板にくぎを好きなだけ打たせた後で、くぎ抜きを使ってそれを抜いてみるように指導する。「こうすると支点と力点について、からだの感覚でわかる。そんな体感が大切です」 「政治をうんと身近に感じてほしい」と、6 年生の社会で地元の再開発にスポットをあてたこともある。中野区が再開発する警察大学の跡地をとりあげ、これから何ができるのか、決めるのは誰かなどを、区役所の担当者や区議会議員を呼んで子供たちからの質問に答えてもらった。 「これから社会を担う世代に、本当に役立つことを勉強してもらいたい」というのが寺田先生の願い。 「うちの学校では算数でも理科でも社会でもどの授業でも“ 考える力” がつくように指導していると思います。夏休みの自由研究は日ごろ身につけたことの集大成。自然科学観察コンクールに応募して全国の作品が集まる中で評価されることは、学校とはまた違うレベルなので、ゴールとしてとてもいい機会だと思います」 |
 校庭の一隅にある菜園 |

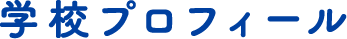
電話 03-3381-7251

寺田礼子先生(56 歳)
「少人数算数」担当
東京都小金井市立南中学校
取材
本物の昆虫とじっくり付き合って ?先輩から後輩へと継続してコツコツ研究を積み重ねる?
じっくりと観察を積み重ねた作品
|
クラブ活動は授業と塾のすきま時間で
| 都市部の中学校の例にもれず、同校でもほとんどの生徒が塾や習い事に通っている。クラブ活動は授業と塾通いの合間をぬって行われる。そんな限られた時間の中でも、継続的な研究が続けられることを今回の作品は証明してくれた。 南中学校の近くには、武蔵野台地の湧き水を水源とする野川が流れている。同クラブは発足時から、野川の水質や周辺の生物の調査、市内の大気汚染などを継続的に調べていたが、渇水して川の水が流れなくなった時、やむなく中断することになった。その時、「ぜひ昆虫をやってみたい」という声が部員からあがり、「小金井の自然環境は本当に豊かなのか、昆虫を通して考える」という調査が2002年からスタートすることになった。 |
 学校のグラウンドは広い。 |
生徒と一緒に模索しながら共同研究
小金井周辺や野川にはどんな昆虫がどれくらいいるのか。中村先生は「調査地点を決めてやった方がいいよ」「季節ごとに集めた方がいいよ」などのアドバイスはしたが、基本的には自由にのびのびと調査が進むように見守る役に徹した。「私は昆虫が専門というわけではないので、指導というより共同研究ですね。一緒に模索しながらやってきました」
観察場所として定めたのは、野川沿いの原っぱや親水公園など6ポイント。まずはデータを集めることに力を注ぎ、夏休みを中心に、毎月のように調査に出かけて昆虫を集めた。最初の年はのべ8日、次の年からは15~16日は屋外で昆虫を採集した。中村先生自身も同行して写真撮影を担当、見つけた昆虫をカメラで接写した。
顕微鏡を専門の図鑑を駆使してコツコツを
|
記録シートは手書きを基本に
| 種類が特定できた昆虫は、A4サイズのシートに記録する。見つけた場所の地図、昆虫の写真、特徴などのコメントをつける。昆虫のスケッチは絵の得意な部員が担当した。この3年間で採集した昆虫は1000を超え、その中から同定できた240種をシートに記録した。 昆虫一覧データはエクセルを使って生徒が打ち込んでいるが、それ以外の部分にパソコンは使用せず、記録は手書きが基本。また、標本も作らない。標本作りやパソコン操作で余分な負担が増えることのないようにという配慮からだ。 |
1枚ずつコツコツ作った |
蓼科の移動教室で自然を観察
理科の自由研究を夏休みの宿題として出すことはしていない。理科の授業のカリキュラム以外で自然に触れるチャンスとしては総合学習の時間があり、2年生のテーマは「環境」。その一環として、6月下旬~7月には蓼科高原への移動教室を実施、今回初めて現地の自然科学の専門家と合同のプログラムを組んだ。生徒の希望に応じて「昆虫」「野鳥」「野生動物」「気象」「地質」の5つのグループにわかれ、それぞれの活動を行う予定だ。
理科の授業の中では、その場でレポートにまとめるよう指示している。授業の最後に時間をとり、実験の結果を短いレポートにまとめて提出させている。レポートはチェックして次の時間に返却している。
研究を通じて市民団体やNPO団体とも交流
これまでも、中村先生は自然科学観察コンクールに何度か応募している。前々回の第43回では、同クラブの生徒による『学校周辺に昆虫はいるのか』が最終選考まで残った。今回の3等賞の受賞は、体育館での朝礼時に全校生徒の前で報告され、部員全員が舞台に上がり、部長が校長先生から表彰状を受け取った。「皆、狂喜乱舞していました。賞品の双眼鏡にも大感激していましたね」
昆虫の調査を継続して行っていることが次第に知られるようになり、小金井市内で昆虫を研究している市民の団体やNPO団体から連絡が入るようになった。今後は学校外の人たちとも昆虫を通して交流をはかれるようになるかもしれないと、中村先生は期待を膨らませている。
先輩から後輩へ受け継がれるデータ
|

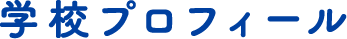
電話042-383-1105

中村江里子先生
2年生担任
理科担当
自然科学クラブ顧問
東京都私立東洋英和女学院小学部
取材
型にはめず、子どもの自主性をたいせつに ?夏休み後、さらに作品に磨きをかけて?
80年代から継続してコンクールへ応募
|
子どもがのびのびできるゆとり空間
| 校庭を囲むように建つ2階建ての校舎は2000年9月に完成したばかり。階段ホールはステンドグラスで彩られ、読書コーナーやフリースペースもあちこちに設けられている。子どもたちがのびのびと過ごせる、ゆったりと明るい空間。旧校舎に比べると教室は1.5倍、校舎全体の延床面積も2倍(8800㎡)になった。身だしなみをチェックできるように、その学年の身長に応じた高さで姿見が教室に設けられているのもほほえましい。 楕円形のテーブルが並ぶ理科室は1階。白いキャビネットには顕微鏡などの備品が納められている。正面の黒板脇には、教育目標でもある『敬神奉仕』の標語が掲げられていた。 |
 新校舎を彩るステンドグラス
|
「自由研究」は選択肢のひとつ
私学の夏休みは公立よりも早く始まる。今年は7月15日が夏休みのスタートだ。柿原先生が出す夏休みの理科の宿題は「自由研究」と「見学記」のどちらか好きな方を選ぶ“選択方式”。
「夏休みには自由研究を頑張ってもいいし、どこかを見学するのでもいい。何かひとつは出してね」
分量も内容もどんな用紙にまとめるかも自由。写真やイラストを入れてもかまわない。この時、自然科学観察コンクールをはじめ、いくつかのコンクールについても紹介、「夏休みの自由研究を応募してもいいし、最初から10月の締め切り日を狙ってもかまわない」と話す。あわせて、研究のまとめ方のヒントとして、自然科学観察コンクールの「自然研究・攻略マニュアル」のコピーを全員に配る。
全員に自由研究を課したこともあるが、「“自由”がいちばん大変。何をしたらいいかわからない」という声も出て、今の形に落ち着いた。全体としては「見学記」の方が多めで、自由研究との割合は3対2ほどだが、両方に挑戦する子どももいる。
「見学記」とは見学レポートのことで、都内の「科学技術館」「たばこと塩の博物館」などはもちろん、近所の川の観察でも、祖父母の畑の見学でも、海外旅行で立ち寄ったミュージアムでもOK。いつもとは違うものに触れるチャンスとして気軽に取り組んでもらうようにしている。
夏休みの“もうひと手間”がポイント
夏休みが終わってからが第二段階。9月以降に“もうひと手間”をかけるのが柿原先生のこだわりだ。
「自由研究を提出した子には、コンクールに応募するかどうかを聞きます。出したいという希望であれば、その作品には赤ではなく鉛筆でチェックを入れ、付箋をつけて、その子に返します」
夏休みの宿題としてはOKでも、コンクールへ応募するとなると作品として形を整える必要がある。
「中身に踏み込むというよりは、主に研究のまとめ方ですね。仮説とまではいかなくても、なぜその実験をしたのか、どんな目的があったのか、何をしたのか、結果はどうなったのか、それを自分はどう考えたのかは必要です。『もう少し、ここをこうまとめれば』『ここに自分の考えを入れるといいんだけれど』などとアドバイス。『もういい』という子どもには、『せっかくここまで頑張ったのに』と駆け引きをすることもあります(笑)」
「秋の追分の生活(5年)」、修学旅行や学芸会の準備など、秋は学校行事も多い。そんな中で再度、研究をまとめ直すのは子どもにとっても粘り強さが身に付くことになる。
頑張った努力が報われる参加賞
「書き直した後、『まだ、ここが足りないね』ともう一度返すこともあるので、子どもたちは大変です。でも、締め切りが10月というのが安心感があるようです。たとえ、夏休み中に研究が終わらなくても、『あと1カ月ちょっと待つからね』と言ってあげることもできます」
そんな努力が報われるのは、参加賞の賞品と努力賞の賞状が届く翌年2月。賞状には柿原先生がひとりずつの名前を筆ペンで入れ、担任から帰りの会で渡してもらう。昨年の第45回は18名が応募、全員が参加賞を受け取った。
「子どもたちにとっては、やはり賞品が魅力ですね。お友達から『いいなぁ』と言われて『頑張った甲斐があったなぁ』と思ったり、『来年は自分も出そう』と決意したりするようです」
また、『入賞作品ガイド集』を見ることで、「この研究すごいね」「こんなまとめ方もあるんだね」と刺激を受ける材料にもなっている。
独自のカリキュラムで英語と情報教育を
|
「理科クラブ」は遊び心を大切に
金曜日の放課後にはクラブ活動の時間がある。柿原先生が顧問を務めるのは「理科クラブ」。現在、5~6年生9名の部員がいる。「年間で20回ほどですが、ブーメランを作ったり、スライムを作って遊んだり、授業でとりあげないことをしています。今、テレビで人気の米村でんじろうさんの科学実験は子どもたちも興味があるようで、今度はしゃぼん玉液には何を混ぜたら伸びるかをしてみたいと言っていました」
マグノリア(泰山木)の木のように
| 小学部の校庭には1本の泰山木がある。春に真っ白な香り高い花が咲くこの木は、旧校舎の頃から子どもたちと先生を見守ってきた。校内音楽会の名称もマグノリア・コンサート。「あの木だけは3年生以上は自由に木登りをしてもいいことになっているんですよ」。卒業生にとっても懐かしいシンボルツリーだ。 「コンクールへの参加が、理科を好きになるきっかけになればいいなと思っています。面白い世界があるんだな、と」と話す柿原先生。 型にはめず、自主性を重んじる。そんな理科の宿題に取り組んだ記憶もいつか懐かしい思い出になるはずだ。今度の夏休み、皆はどんな新しい世界に出会えるだろう。9月になるのが待ち遠しい。 |
 土のグラウンド。奥に見えるのが泰山木 |

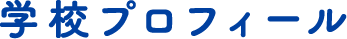
電話 03-5411-1322

柿原直子先生
理科専任(4~6年)
東京都私立城北中学校
取材
実験・観察を多く取り入れた理科の授業
城北中学校では、理科の授業に実験・観察を多く取り入れている。これは、理科は机上の学問ではなく、実験や観察を通して身につけていくものだという信念に基づいているからだ。
また実験や観察から得られたデータや事実を整理してまとめることにより、科学的な思考力が身につくという認識に立って、必ずレポートにまとめるようにしている。レポートの提出は、平均すると月2本ぐらいになる。実験をする前には必ず予習を課しており、終わったら結果、考察、感想をまとめて翌週提出する。
レポートの書き方、書式は、1年次に徹底的に教え込む。実験のやり方も、基本操作から指導する。小俣先生は、「かた付けもうるさく言っていますよ。それと躾けですね。1年生、2年生はとくに。授業の前に『静座』をさせることもあります」とのこと。
理科教育に恵まれた環境
小俣先生は中学で生物と化学を教え、高校では理系進学コースの生物を教えている。
中学、高校の理科の先生は、小俣先生を含めて専任が11人、講師9人、それと実験助手が4人いる。小俣先生は「助手の皆さんは二部の学生だったり教員志望の人たち。こうした若い人が生徒と接しながらいろいろなところでバックアップしてくれているから、レポート指導や自由研究ができている」と教員、助手のチームワークを強調する。
また、恵まれた実験設備を持っていることや熱心に取り組む生徒の姿勢も、実験、観察主体の授業ができる背景だという。
中学生全員がチャレンジする夏休みの自由研究
夏休みの自由研究は、城北中学生の必修課題となっている。
夏休みが明けた9月1日、800点余の作品が一斉に届けられる。理科の先生たちは全員で、これから2~3日かけてすべての作品を審査し、物理、化学、生物、地学の分野別に、金賞、銀賞、銅賞、努力賞を選びだす。
学年ごとに選ばれる点数に制限はないが、昨年の例では各学年金、銀、銅賞が40~50作品選ばれている。そのうち金賞は1年生が2点、2年生は3点、3年生は11点だった。
金、銀、銅賞に入賞した生徒は、城北学園文化祭(9月末)に向けて発行する「中学理科夏休み自由研究優秀作品集」に載せる原稿を用意しなければならない。金賞受賞者は文化祭の中学理科展示コーナーに展示するために、模造紙にレポートを作成する。時間があまりないため、生徒たちはクラブ活動の空いている時間などを見つけて作ることになる。
文化祭に展示された金賞受賞作品は、その中からさらに、アンケートによる評価などを参考にしてもっとも優れた3点が選ばれる。この3作品の受賞者は、後日、講堂で中学生全員と父母などを前にして発表する場が与えられる。会場は900人を超える大聴衆。パソコンのパワーポイントを使って、舞台上のスクリーンにデータを映し出しながら、原稿を見ないで発表する。持ち時間は15分。
夏休み自由研究は20年以上前から続いており、優秀作品集は16、17年前から作っているそうだ。
自由研究のテーマは夏休み前に提出
| 夏休みの理科自由研究で求められることは、「身近な疑問について夏休みを利用して自分で解決してくる」となっている。漠然としているが、研究に取り組むためにはテーマを決めなければ進まない。 テーマを見つける参考資料として、小俣先生は「中学理科夏休み自由研究優秀作品集」を挙げる。この作品集は全生徒に配られており、先輩たちが過去にやった実験、観察をヒントにすることを勧めている。「市販の本を参考にしても構わないが、自分なりのスパイスで味付けすることが大切」と小俣先生。 自由研究をスムーズに進めるために、城北中学では夏休みに入る前にテーマを提出させている。今年は7月1日付けで「理科自由研究のお知らせ」を全員に配布。研究の内容、レポート用紙のサイズ指定、提出日、提出方法などの指示があり、研究例(進め方)や研究計画書が添えられている。この中に「テーマがぎりぎりまで決まらずにいると、不本意な内容になってしまうことが多いようです。そこで、夏休みになる前に何を研究するのか決めておけばより充実した自由研究を行えます」と、テーマ決めの意義が書かれている。テーマ、内容、実験観察を記入する研究計画書の提出締め切りは7月16日、終業式の日とあった。 |
 広大な敷地が広がる城北学園の正門 |
上野動物園を校外見学
城北中学がいま力を入れているものに、校外見学がある。1年生はこの7月、上野動物園に行った。生徒にはいくつかの課題が与えられ、動物の中でもとくに脊椎動物に絞って観察した。生物の中の脊椎動物を勉強するための導入として上野動物園が位置づけられたのだった。動物園の指導員の方に30分ぐらいのお話もしていただいた。
校外でのこうした活動は自由研究のテーマを選ぶヒントになっているようだ。生徒の中には、1年を通してデータ収集に没頭したり、中学3年間をかけて研究に取り組む生徒もいる。
「レポートは手書き」にこだわる小俣先生、教科書も手づくり
「私がいちばんこだわっているところですが」と小俣先生は「レポートは手書きでなければいけない」と言う。このことは理科の先生に共通していることで、「夏休み自由研究優秀作品集」には手書きのレポートがずらり並んでいる。
小俣先生はまた、「理科が好きな子にはどんどんチャンスを与えてやりたい。眠っている原石を磨いて、光らせたい」とも。理科に興味を示す子には、とことんサポートしてあげる。器具でも薬品でも、何でも提供してあげる。
もう一つ、私学ならではの特徴もある。それは、生物や化学の理科の教科書を先生たちが自分たちで作っていることだ。「中学でやる内容を上に上げたり、上の学年でやる内容を下に下ろしたりするんです。ですから市販の教科書では対応しきれない」と小俣先生。6年間というスパンで考えたカリキュラムに合わせて、教科書も問題集も自らの手で作っている。
盛んなクラブ活動
城北学園は進学校だ。高校の進路先をみると、国立大学や有名私立大学に大勢進学している。しかし、「勉学・クラブ活動の両面より各自の個性伸長をはかって」と教育方針にあるように、課外活動にも熱心に取り組んでいる。昨年の中学の成績を見ると、サッカー、弓道、ソフトテニスや卓球などで、東京都の上位に進出している。
文化部系もがんばっていて、小俣先生が顧問をしているアマチュア無線の「ラジオ部」は、「その世界ではかなり有名」だとか。OBとのつながりも強く、今年の夏合宿には8人が参加して、アマチュア無線の国家試験の勉強を手伝ってくれた。小俣先生がもう一つ顧問をしている生物部も、その活動が雑誌に紹介されたりしている。
応募に当たっては、もう一度指導しなおす
|

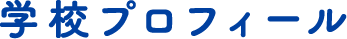
電話 03-3956-3157
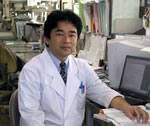
小俣 力先生(44歳)
中学1年学年主任
生物担当
東京都青梅市立西中学校
取材
一年次から1人ずつレポート指導 A評価をもらうまで書き直す
実験のたびに1人1人がレポートを提出
清水先生の理科指導の基本は、レポート提出だ。必ず個人で書くように指導している。
班で1枚というようなことはやらない。グループでやると、その中のリーダー的生徒が引き受けて、他の生徒はその生徒にまかせてしまう傾向があるからだ。だれかにくっついてやるのではなくて、自分でどこまでできたかということを大事にしている。
人任せにしないということでは、実験は男子だけの班、女子だけの班にしてやる。男女いっしょにすると、女子が記録係、男子が運び係といった役割分担ができてしまうからだ。
いま、理科の授業は週2時間だけになってしまった。そのため、実験は教科書に載っているものだけで精一杯になっている。
最初から真っ白い用紙にレポートを書く
|
実験の方法は絵で描かせる
| レポート指導は1)テーマ、2)目的、3)器具と材料、4)方法と結果、5)考察、6)感想、の項目でまとめるようにしており、方法は必ず絵で描かせている。絵で描くのは、あとで前にやった実験を思い出せるようにするためだ。 レポートは実験をやるごとに書かせており、1学期で10本から15本ぐらい。1年だと30本ぐらいになる。 何も書いてない真っ白いレポート用紙を使用し、枚数制限はしていない。 3年生になると、全員が45分または50分の授業中に書き上げるようになる。このことは、生徒の自信となっている。 |
 |
「A」をもらうまで書き直す
提出されたレポートは、すべてABC評価をする。
例えば考察がこの子はわかっていない、ということだとその子のレポートはBとかCにして返す。返された子はどこがいけないのかを考え、書き直して再提出する。それを「A」の評価がもらえるまで、何回でも繰り返す。
1学年は約140人。1人ずつ、年間30本ぐらいあるレポートのすべてを「A」になるまで見ていく。
思った以上にたいへんなことだが、基礎をつくることなのできちんと教えていきたい。ここの生徒はみんなまじめに取り組んで、がんばってやっている。
「まとめレポート」で書く練習
清水先生が、「私のやり方は珍しいかもしれません」と言うのが、通常のレポートとは違う「まとめレポート」だ。
それは教科書を色ペンでチェックしていく方法で、実験の目的は何色、答えは何色と決めて色ペンで塗っていくやり方だ。重要語句も色を塗ってチェックする。
こうして、色分けされたものを「まとめレポート」としてレポート用紙に写させる。これは1年次と2年次にやらせており、教科書の内容を理解させるため、レポートを書く訓練として採り入れている。文章の書き方の基礎を養うことにもなる。
書くことは、訓練しないとできない。とくに考察は何を書いたらよいかわからない子が多い。そこで、教科書から目的や考察を見つけて、まず写させる。そのあとで、自分がやった実験からわかったことを、自分の言葉で書くようにさせている。
3年生になると教科書を読み取れるようになるため、色ペンチェックは不要となる。
夏休みの自由研究は「自分でやること」を徹底指導
1年次、2年次は、夏休みの宿題に自由研究をやらせている。
何をやるか、テーマを探すのはたいへんなことなので、「本を見てもいい」「本からテーマを選んでもいい」「真似をしてもいい」。ただ、必ず自分でやるようにさせている。
例えば、しゃぼん玉なら自分で吹いてみる。吹いてみれば、何か工夫するようになる。そこで工夫したことは、自分のレポートに取り入れることができる。
本に書いてあるとおりにはまずいかない。自分で実験を始めてみれば、やっていくうちにどこかでとっかかりがでてくる。自分でやることで、いろいろ考えるようにもなる。
「努力賞」をもらうことが励みに
|
中学でしかできないことをやらせてあげたい
| 西中のように自然に恵まれた地域でも、魚を手でつかむ子はほとんどいない。実験でメダカを使う時にも、水槽から網ですくって持ってきている。 それでは、メダカの感覚が伝わってこない。だから、できるだけメダカを手にとって持ってくるようにさせている。カエルの解剖をした時も、自分で解剖するのだから自分の手で持つようにと言った。中にはイヤな実験もあるだろうが、イヤだと言ってたら、カエルを持つなんてことは一生ないかも知れない。 清水先生が理科の授業でいちばん重視していることは、「触れてみる」こと。いろいろ触ってみることができるのは、中学生時代しかないと思っている。イヤなものでも触ってみる、やってみる。こうして中学で、いろいろなことをみんなに経験させてやりたい。 普段の授業の中でみんなが理解し、みんなが同じように体験していくことができれば、それはとてもすばらしいことだと思っている。 |
 |

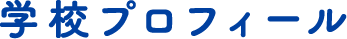
電 話/0428-76-0114

清水弘子先生(50歳)
理科担当(3年生担任)
専門は生物

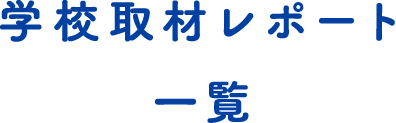
-
北海道(1)
-
秋田県(2)
-
福島県(1)
-
茨城県(2)
-
群馬県(2)
-
埼玉県(1)
-
千葉県(2)
-
東京都(6)
-
富山県(1)
-
長野県(1)
-
岐阜県(1)
-
愛知県(1)
-
京都府(2)
-
福岡県(1)
-
鹿児島県(1)










 校庭に面した明るい理科室
校庭に面した明るい理科室